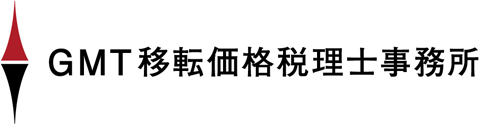取引単位営業利益率法を採用していた場合の課税事例
ある電気機器造業者が、中国に製造子会社を設立しました。
当該製造子会社は、日本から技術供与を受け、原材料は現地で調達し、現地で販売を行っていました。日本に支払う無形資産の対価として、業界での相場に基づきロイヤリティ料率をA%と設定していました。
それから数年後、中国でのマーケットが拡大し、中国製造子会社の利益率は上昇していきましたが、ロイヤリティ料率はA%のままで事業を行っていました。
その後、日本で税務調査が入り、過去数年分について当該中国子会社の適正な所得水準を検証するため比較対象会社を選定したところ、選定された比較対象会社の利益率と製造子会社の利益率が大きく乖離しており、ロイヤリティの取り漏れとして課税されました。
コメント:移転価格税制上、ロイヤリティ料率の算定は、業界での相場や他の類似契約における料率との比較分析により設定を行う方法はあまりとられず、実務上は現地法人の収益性をベースに料率を算定する方法が主流となっています。相場的に十分と思われる料率を回収していたとしても、移転価格税制上は所得移転とみなされるケースも少なくないため、特に利益率の高い海外子会社については、対価の回収漏れを指摘される可能性がないか、注意が必要です。
固定ロイヤリティと変動ロイヤリティ
ロイヤリティの支払いは、毎年固定の料率を売上高に乗じて算出された金額を支払うことが一般的かと思われます。 しかし、移転価格税制は、関連者間取引を独立企業間の条件で行うことを目的とするものではありますが、ロイヤリティの算定にあたっては、固定ロイヤリティの考え方はあまり取られません。
企業担当者にとっては、ロイヤリティ料率を毎期変動させることについて違和感があり、実務上も手間がかかるため、ロイヤリティ料率を毎期変動させることに抵抗がある企業が多いのも事実です。
しかし、よく考えてみると、独立企業間では、技術供与によって利益が出なければ、ロイヤリティの減額を使用者側が交渉するでしょうし、使用者の取り分があまりに大きくなれば、無形資産の所有者はロイヤリティ料率を上げることを交渉するでしょう。関連者間ではこのような交渉が行われないため、固定のロイヤリティ料率を永続的に適用することにはやはり所得配分上問題が生じ得ます。
実務においては、社内ルールをきちんと設定し、経理実務と移転価格税制の遵守を同時に達成できるような料率設定をしていく必要があるものと考えられます。